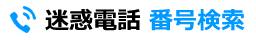電話勧誘販売と特定商取引法のポイント
本ページでは、電話勧誘販売に適用される「特定商取引法」の基本的なルールについて解説します。 電話での勧誘を受けた際に、事業者にはどのような義務があるのか、消費者にはどのような権利が認められているのかを知っておくことで、 不本意な契約やトラブルを防ぐことにつながります。
電話勧誘販売とは
- 定義:事業者が電話をかけて商品・サービスの契約を勧誘し、その結果として消費者が契約を締結する取引が「電話勧誘販売」に該当します。
- 対象商品・サービス:健康食品、投資商品、リフォーム、光回線、電気・ガスの切り替えなど、さまざまな分野が対象となり得ます。
- 対象となる相手:原則として、一般消費者が相手方となる取引が保護の対象です。
事業者が守るべき主な義務
- 事前説明義務:事業者名、担当者名、勧誘目的(販売したい商品・サービスの種類など)をはじめ、契約条件・料金・支払い方法などを分かりやすく説明する義務があります。
- 不実告知の禁止:事実と異なる説明や、重要な事項を故意に伝えない行為は禁止されています。
- 威迫・困惑行為の禁止:大声で威圧したり、不安をあおるような言動により、消費者に判断の余地を与えない勧誘は違法となる場合があります。
- 再勧誘の禁止:消費者がはっきりと断った後に、同じ内容の勧誘を繰り返すことは特定商取引法で禁止されています。
クーリング・オフ制度について
- クーリング・オフとは:一定期間内であれば、消費者が一方的な意思表示により契約を無条件で解除できる制度です。
- 期間:電話勧誘販売の場合、原則として書面(契約書面など)を受け取った日から一定期間(通常8日間)内であればクーリング・オフが可能とされています。
- 対象とならない場合:一部の商品・サービスや、事業者を相手にした取引など、クーリング・オフが適用されないケースもあります。詳細は公的機関等の情報をご確認ください。
不審・不適切な勧誘を受けた場合の対応
- その場で契約しない:勧誘を受けても、その場で決断せず、必ず一度持ち帰って家族や第三者に相談することが重要です。
- 内容を書面で確認する:契約書面や重要事項説明書の内容をよく読み、疑問点があれば事業者や専門機関に確認しましょう。
- 不安を感じたら相談:不実告知や威迫的な勧誘が疑われる場合は、消費生活センターなどの公的機関への相談を検討してください。
本ページの内容は、特定商取引法の概要を分かりやすく説明することを目的としたものであり、法的な解釈を確定するものではありません。 具体的なトラブルや契約内容については、必ず公的機関や専門家にご相談ください。
掲載日
運営:電話トラブル対策センター
代表 山田 幸俊
関連情報: 再勧誘の禁止(電話勧誘のルール) | オプトアウト(電話停止の申し入れ方法) | 迷惑電話の相談窓口一覧 | 迷惑電話の種類と特徴まとめ