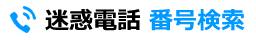再勧誘の禁止について
本ページでは、特定商取引法に定められている「再勧誘の禁止」について解説します。 一度断ったにもかかわらず繰り返し行われる電話勧誘は、法律で禁止されている場合があります。 どのような行為が再勧誘にあたるのか、またしつこい営業電話を受けた際にどのように対応すればよいかをまとめました。
再勧誘の禁止とは
- 再勧誘の定義:特定商取引法では、消費者が「必要ありません」「契約しません」などと明確に断ったにもかかわらず、同じ事業者が再び勧誘を行うことを禁止しています。
- 対象となる取引:電話勧誘販売や訪問販売など、一部の取引形態については再勧誘の禁止が明文化されています。詳細は消費者庁など公的機関の情報をご確認ください。
- 目的:消費者が心理的圧力や執拗な勧誘によって不本意な契約を締結させられることを防ぐことが目的です。
違法となり得る再勧誘の具体例
- 一度「不要」と断った後、同じ事業者から短期間に何度も電話がかかってくる。
- 「忙しいので」と断ったにもかかわらず、時間帯を変えて同じ勧誘が繰り返される。
- 家族が断った後に、別の家族宛てに同じ内容の勧誘電話を何度もかけてくる。
- 「二度とかけないでほしい」と伝えたにもかかわらず、再度勧誘を行う。
このような行為は状況によって違法な再勧誘に該当する可能性があります。
再勧誘を受けたときの対処方法
- 断った事実をはっきり伝える:「以前もお断りしました」「今後一切電話しないでください」など、拒否の意思を明確に伝えましょう。
- 通話日時・相手先をメモする:電話番号、事業者名、担当者名、通話日時、勧誘の内容などをメモしておくと、相談・通報時に役立ちます。
- 録音の活用:可能であれば通話内容を録音しておくと、トラブルになった際の重要な証拠となります。
- これ以上の連絡を拒否する旨を伝える:「名簿から削除してください」「今後一切勧誘しないでください」と具体的に伝えることも有効です。
相談窓口と通報先
- 消費生活センター:お住まいの地域の消費生活センターでは、再勧誘を含む電話トラブル全般について相談を受け付けています。
- 消費者ホットライン(188):局番なしの「188(イヤヤ)」から、最寄りの相談窓口につながります。
- 行政機関・監督官庁:事案の内容に応じて、消費者庁や各種監督官庁が対応する場合もあります。相談時に紹介される窓口の案内に従ってください。
しつこい勧誘や不安を感じる行為が続く場合は、一人で抱え込まず、早めに公的機関に相談することをおすすめします。
本ページの内容は、一般的な解説を目的としたものであり、個別の事案についての法的判断・助言を行うものではありません。 具体的なトラブルに直面している場合は、必ず公的機関や専門家にご相談ください。
掲載日
運営:電話トラブル対策センター
代表 山田 幸俊
関連情報: オプトアウト(電話停止の申し入れ方法) | 電話勧誘と特定商取引法のポイント | 迷惑電話の相談窓口一覧 | 迷惑電話の種類と特徴まとめ